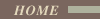不動産の鑑定評価を生業に! |
平成5年1月31日付けを以って、銀行の、当時は関連会社であった不動産会社へ出向を命じられました。
長野冬季オリンピックを招致しようと、その関連施設用地の買収が進められていましたし、同時に、長野駅東口の再開発事業も始まっていました。不動産の鑑定評価に対する需要が非常に多くあったのです。 たまたま、私は、若い頃に「不動産鑑定士」の資格を取得していたし、年齢的にも、決して若いとは言えないけれども、年を取り過ぎてもいない、しかも、長野市生まれの長野市育ちで、「土地勘はある!」など、必要とされる全ての条件を満たしていたこともあって、私にお鉢が回ってきたのだと思います。 それは、私にとっては、大袈裟に言えば、人生の転機とも言うべきことでした。 以後、不動産の鑑定評価の仕事が、私の本職になったのですから・・・。まさか!まさか!この年になって、銀行員から、不動産の鑑定評価を生業にする仕事に就こうなどとは!夢にも思ってはいないことでした。 不動産鑑定士には、いわゆる「転職組」も比較的多いのです。しかし、彼らは、銀行員にはない多くの人生経験を持っています。その意味で、銀行という一つの「枠」の外に、多くの「いい友人」を得ることが出来たことは、今になって考えてみれば、結果として、この「転進」は幸せであったとさえ思っています。 しかも、長野冬季オリンピック関連施設用地の買収や長野駅東口の再開発などに絡む鑑定評価は、地方の不動産鑑定士にとっては、なかなか経験する事が出来ないような大型の案件が多く、非常に多忙ではありましたが、不動産鑑定士としての「腕」を磨くことも出来たと思っています。 その後は、「地価公示」や「長野県地価調査」の仕事に従事しました。この仕事の労力たるや、大変なものでした。 しかし、これらの仕事は、鑑定評価の、言わば「基礎的」「基本的」な部分に当ると言っていいでしょう。 この経験が、その後の仕事に、大いに役に立っていることは言うまでもありません! |
| HOME|(財)長野経済研究所と私!|「法務ニュース」を発行する!|不動産の鑑定評価を生業に!|鑑定業界の話題あれこれ!|歌手・島津亜矢を語る!|温泉愛好者大集合!|徒然なるままに!|掲示板「亜矢姫倶楽部」 |
 |
 「時事法務の諸問題」を自費出版する! 「時事法務の諸問題」を自費出版する! |
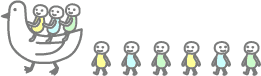 |
不動産鑑定士としては、仕事に追っかけられているような忙しい日々が続きましたが、もう、自分も還暦を迎えようとしているある年の夏、自分の歩んできた「足跡」を何とかして、残しておきたいという願望が涌いてきました。 その時に思い付いたのが、長野経済研究所時代に、折りにふれて書き残していた小論文の幾つか、勿論、そのベースになっているものは「法務ニュース」ですが、これらを何とかして、一冊の本に纏めて、「自費出版」でいいから、発行する事は出来ないかという構想でした。 しかし、執筆した当時は「新法」と言い、あるいは「改正法」と言っても、その後、幾度かの改正がなされているし、学説・判例も変遷を示している、今、ここで発行することにいかほどの意義があるのか、それは随分と悩み考えました。しかし、「自分は、学者ではない。その本に学問的意義を持たせようと考えること自体おかしなものではないか、ただ、自分の歩んで来た『足跡』を残せれば、それでよいのではないか」と考え、発刊に踏み切りました。 最も悩んだのが、本のタイトルです。多くの候補の中から、最終的には、「時事法務の諸問題」という題名を選びました。また、校正が実に労力の要る仕事で、会社の仕事を終え帰宅して、夕食後、毎晩のように12時過ぎまで掛かりました。たった一冊の本でも、「出版」をするということはこんなにも大変な仕事なのか!と、その時、つくづく思ったものです。 いずれにしても、自分が経済研究所に在籍中ならともかく、不動産鑑定士としての仕事をしながら、その片手間にやった仕事ですから、その苦労は並大抵なものではありませんでした。それだけに、出来上がった時の喜びは、格別なものがあり、涙が出てきそうでした。 「棺桶に入れて欲しい」と遺言しておきたいと思うくらいに感激したことを憶えています。 内容的には、古い論考の「寄せ集め」にすぎないものですが、生涯にたとえ一冊でも、自分の歩んで来た「足跡」を自著という形で遺すことが出来たということは、非常に幸せなことだったと思っています。 |
 |
 「土地神話」の崩壊! 「土地神話」の崩壊! |
戦後の我国では、地価が高騰した時期が3回ありました。 1回目の地価高騰は、高度経済成長を背景として、昭和30年代半ばに起こりました。 2回目の地価高騰は、昭和47年から48年に起こりました。国際金融情勢に因る過剰流動性と、「列島改造ブーム」による企業の事業用地の取得や大都市への人口集中などによる旺盛な土地需要により、土地を利用するのではなく、転売して利益を得る事を目的とした「投機的」な土地需要が増大しました。 こうして、土地は所有しているだけで価値が増大する有利な資産であるという「土地神話」が形成されたのです。 3回目の地価高騰は、いわゆるバブル経済によって起こりました。それまでに定着していた「土地神話」は、地価の上昇に対する過剰な期待感から、投機的土地取引を頻発させました。 バブル期の地価高騰は、大都市圏では平成3年の後半から顕著な下落傾向を示し、今では、住宅地は昭和62年頃の水準、商業地は昭和55年頃の水準にまで下落しています。 かくして、「土地神話」は完全に崩壊し、土地は所有しているだけで価値が上昇するという「有利な資産」ではなくなったのです。今や土地は「所有」から「利用」の時代への転換期に差しかかっているのです! |
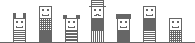 |
 |
 収益性や利便性重視の市場へ! 収益性や利便性重視の市場へ! |
 |
最近の地価動向の特徴として、収益性や利便性重視の高い地点では、下落幅が縮小する傾向を示す一方、収益性や利便性に劣る地点では、依然として、顕著な下落傾向を示すという地価の「個別化」の傾向が窺えます。 特に東京都心部の住宅地や商業地のうち、立地条件の良い地点では、上昇局面に転換しています。 これは、資産としての有利性が注目される土地市場から、収益性や利便性といった、実需を前提とした効率性重視の市場へと変化してきていることのあらわれと言えるでしょう。今こそ、土地の適正な利用を推進し、職住のバランスのとれた都市改造への再編ー「都市再生」ーをダイナミックに推進してゆく必要があります。 |
 |
 収益性を重視した鑑定評価へ! 収益性を重視した鑑定評価へ! |
これまでの鑑定評価の方式には、原価方式、比較方式、収益方式の3手法があり、等しく尊重されていました。 しかし、バブル経済の崩壊後の社会経済構造の変化を背景に、資産性・収益性を重視したマーケットへと移行したことや、不動産の証券化の伸展などにより、不動産の鑑定評価においても、投資用不動産を土地建物一体の複合不動産としてとらえ、そのキャッシュフローを価格に的確に反映させる評価への要請が強まってきました。 このように多様化・高度化した要請に対応するため、収益還元法の重視と、収益性をより的確に把握するために詳細な市場分析や、対象不動産の詳細な調査が、重要になってきました。 これらの要請を受け、平成15年1月1日からは、新しい「不動産鑑定評価基準」に基づいて、鑑定評価が行なわれています。 (注)収益還元法とは、不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の合計額をもって、不動産の経済価値とする手法です。 主に単年度の純収益を総合還元利回りで還元して求める「直接還元法」と、多年度の純収益を期待収益率で割り引く「DCF法」があります。 「DCF法」は、連続する複数の期間(例えば10年間)に発生する純収益及び復帰価格を、その発生時期に応じて割り引き、それぞれを合計することによって、不動産の収益価格を求める手法です。 |
 |
 |
| HOME|(財)長野経済研究所と私!|「法務ニュース」を発行する!|不動産の鑑定評価を生業に!|鑑定業界の話題あれこれ!|歌手・島津亜矢を語る!|温泉愛好者大集合!|徒然なるままに!|掲示板「亜矢姫倶楽部」 |
|