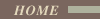「債権管理の手引き」を作成する! |
「債権管理教室」での講師や、企業・団体が主催する講演会における講師を務める機会が多くなるにつれ、何か適当なテキストになる本はないものかといろいろ当ってはみましたが、あるものは専門的に過ぎ、また、あるものはハウツーもので安直に過ぎ、なかなか適当なものがない、それでは、いっそのこと自分で作った方が手っ取り早いと思い、テキスト本の作成に取り掛かりました。
その当時、東京の八丁堀にある(社)商事法務研究会の中に、企業の法務担当者の勉強会とでも言ったらいいのか、「経営法友会」という任意の団体があり、私もメンバーになっていました。その「経営法友会」で「債権管理マニュアル」というものを作成していたので、それを参考にして、自分なりきに味付けをし、「債権管理の手引き」という小冊子を作りました。副題は「〜売掛債権の管理と回収〜」としました。B5版で、102ページ程度の簡単なものです。 これを作成するに当っては、専用の原稿用紙を印刷してもらい、表紙のデザインの選定まで、全部を自分一人の手でやったので、今でも、かなりの「思い入れ」があります。 |
| HOME|(財)長野経済研究所と私!|「法務ニュース」を発行する!|不動産の鑑定評価を生業に!|鑑定業界の話題あれこれ!|歌手・島津亜矢を語る!|温泉愛好者大集合!|徒然なるままに!|掲示板「亜矢姫倶楽部」 |
 |
 未然に焦付債権の発生を防止する! 未然に焦付債権の発生を防止する! |
 |
「債権管理の手引き」は、あくまで「売掛金の管理と回収」をテーマにした研修会や講演会で使用するためのテキストとして作成したものです。同時に、手頃な参考書的な意味合いをも持たせようとしたので、出来るだけ専門色を薄め、「解り易さ」を心掛けて書いたつもりです。 このテキストの「はじめに」には、こう書いてあります。 「『回収なくして販売なし』とは、しばしば言われることですが、その一方で、『回収に決めてはない』ということも現実のすがたのようです。 きびしい販売競争に打ち勝って、売り上げを伸長することは容易なことではありませんが、せっかく売っても、売掛金の管理がおろそかであったために、売却代金の回収ができなくなってしまえば、それまでの苦労は水の泡に帰してしまいますし、ときには企業の存続すら危うくなりかねなりません。(中略) この小冊子では、売掛金の企業経営に及ぼす影響からはじまって、焦付債権をつくらないためには、取引先企業のどのような兆候に留意したらよいかを考え、不幸にして焦付債権を発生させてしまった場合にはどのような方策をとって回収をはかっていったらよいかにいたるまでを、簡単にまとめたものです。 これからの経営管理や社員研修などで、『手引き』としてお役に立てれば幸いです。」 つまり、危険な兆候の把握からはじまり、不幸にして取引先が倒産し、法的整理の手続きに入った場合の対処の仕方に至るまでを、言ってみれば、浅く広く解説を試みたつもりです。幸いにして、この試みは、効を奏し、いまだに版を重ねていると聞いています。 いずれにせよ、私は、この「債権管理の手引き」とその後に書いた「営業マンのための法律知識」の二冊の刊行物を残すことよって、「長野経済研究所」に自分の「足跡」を残すことが出来たと思っています。 |
 |
 「営業マンのための法律知識」を書く! 「営業マンのための法律知識」を書く! |
これは、研修のテキストとしてではなく、専ら経済研究所が発行し、販売する刊行物として書いたものです。 もっとも、研修教室として「営業マン研修」という研修教室も、これは私の担当ではありませんが、開催していたので、そちらの方で参考になれば・・・という意味合いを持たせようとも目論んでいました。その点では、「債権管理の手引き」の姉妹編という位置付けも持っていました。 この本は、商取引の前提となる「契約および契約書」、回収方法としての「手形・小切手の扱い方」、債権保全のための「担保・保証」、「債権回収の具体策」の四つを柱に構成されています。 こちらも、「解り易く」を心がけて書いたつもりです。 出来映えは、むしろ、こちらの方がいいのではないかとすら、自分では思っているのですが、なぜか売行きは余り芳しいものではありませんでした。 今でも、一冊1000円で販売しています。 「債権管理の手引き」も「営業マンのための法律知識」も、「編集 長野経済研究所」になっています。従って、私に著作権はありません。発行はともかくとして、著作者として、自分の名前を入れておけば良かったと後悔しています。 |
 |
 |
| HOME|(財)長野経済研究所と私!|「法務ニュース」を発行する!|不動産の鑑定評価を生業に!|鑑定業界の話題あれこれ!|歌手・島津亜矢を語る!|温泉愛好者大集合!|徒然なるままに!|掲示板「亜矢姫倶楽部」 |
|